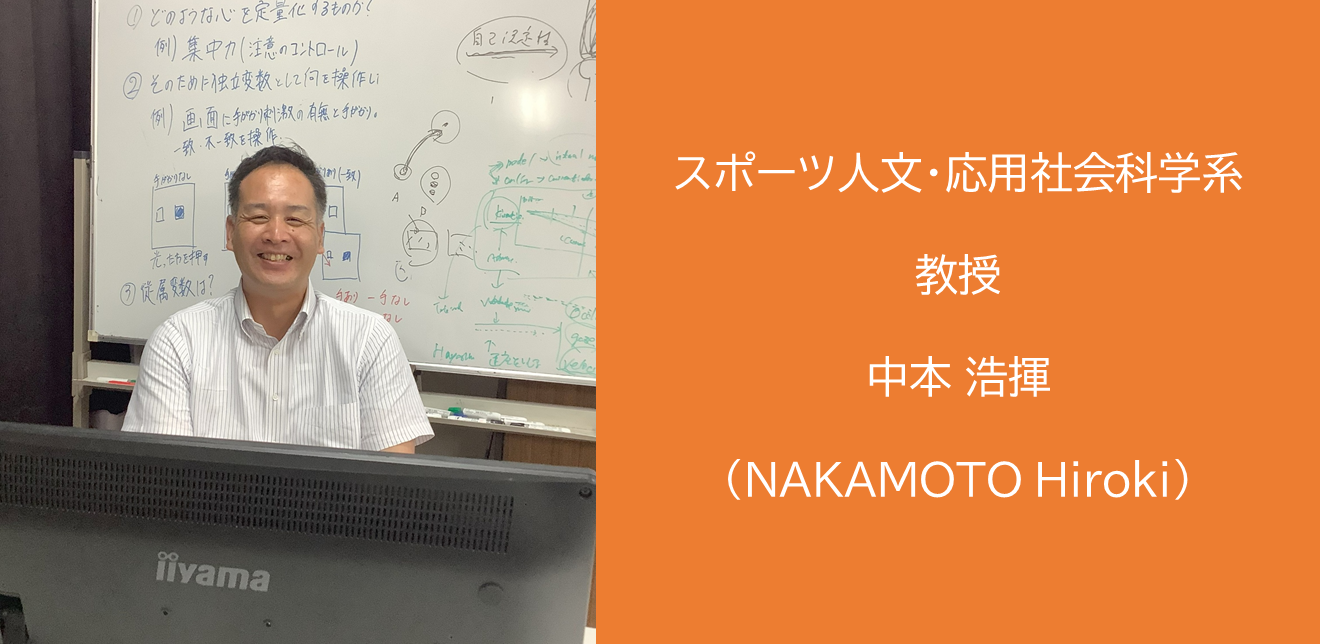
人の話に真摯に耳を傾ける誠実さと、話していると周りの空気までほのぼのとしてくるやさしいオーラがある。スポーツ心理学を専門とし、中本浩揮先生の講演を聞いた人々からはすこぶる評判がよく、時代の最先端を行く中本ゼミも人気だ。趣味は「食べること」だと笑うが、さらに突っ込むと決してグルメなわけではなく、「家族や友人たちとの会話を楽しみながらの食事が好き」なのだと分かった。学生には「とにかく楽しんで!」と精一杯のエールを贈る。ピンチをチャンスに変えて、研究者の道へ。“コミュニケーション能力ゼロ”との自己分析とのギャップもまた、面白い。
中本先生の研究内容をひとことで教えてください。
中本 研究の最終目標、ゴールをひとことで言えば「人を幸せにできたらいいな」です。スポーツが上達して楽しい気持ちになれたらとか自分の目標や夢が達成できたとか、そんなことにつながる研究がしたいなって思っています。もちろん、自分も幸せになるために。
岡山県から東京学芸大学に進学したのは?
中本 国立で野球が強い大学が、当時東京学芸大学だったんです。プロ野球選手になった先輩に続きたかったのですが夢かなわずで、高校野球の監督になって岡山県から甲子園を目指そうと思っていました。ところが教員採用試験に落ちてしまって。同じ野球部でキャッチャーだった友人に進路を尋ねたら、大学院に行くと言うので、昔からスポーツを理論的に考えるのが好きだったこともあり、「じゃあ俺も大学院に行こう!」ぐらいの軽いノリで大学院への進学を決めました。
実際に大学院に進学してみていかがでしたか。
中本 野球部の監督から学芸大にスポーツ心理学の第一人者、杉原隆先生がいることを聞いて、その先生の研究室に入ったのですが、自主性に任せてくれる指導スタイルと、そこで出合った“知覚”の世界にドハマりして、それまで勉強はあまり好きじゃなかったのに、大学院ではたぶん、だれよりも勉強したんじゃないかなと思います。博士課程はお茶の水博士みたいな人たちが行くところで、自分には関係ない世界だと思っていたので、再度教員採用試験を受けたのですがまた不合格でした。それで修士課程修了後は一般財団法人田中教育研究所に勤務しながら、学芸大の教務補佐員として授業をやらせてもらっていたのですが、それがとても楽しくて、やっぱりこういう世界って性に合うなあと思って1年後に博士課程に行くことを決めました。
博士で鹿屋体育大学に進学したのは?
中本 修士課程のときの指導教員だった杉原先生に相談したところ、「俺、もう退官だから」って言われて。それで、師弟関係にあった森司朗先生を紹介してもらい、森先生が学芸大から鹿屋体育大学に移るというので鹿屋を受験しました。友だちと先生に流されてきた人生ですが、ここ鹿屋のスポーツ科学を学べる施設と環境に触れた時の衝撃と感動は、もうワクワクしかなかったですね。
博士修了と同時に本学に採用になりましたが、教員として感じている魅力は?
中本 「国立大学唯一の体育系単科大学」ってフレーズはみんなよく口にするけれど、これって実はすごい幸福なことだなと思っています。要は国がうちの大学から体育・スポーツのことを発信して先導しなさいって言ってくれているってことなので、大学の教員としての責任もあるし、自分自身はスポーツ心理学の専門なので、その分野に関する学問をけん引したり、鹿屋からメッセージを出していけたらカッコいいな~といったところを目指せるというのが、本学教員としての魅力だと思います。
アムステルダム自由大学で過ごした1年間の客員研究員時代について、教えてください。。
中本 専門は知覚運動制御という領域なのですが、アムステルダムに留学したことで、ヴァーチャルリアルティ(VR)との出合いがありました。修士時代から、知覚トレーニングという映像を使ったトレーニングによって、中学生の野球選手の予測能力を伸ばす、といった研究を続けてきたのですが、VRは自分がやってきた研究を現場に落とし込んで、スポーツが上達することをサポートする強力なツールになるということを実感できました。現在も知覚運動制御×VRってところで研究を続けていますが、実際に野球部の学生に使ってもらって、喜ばれています。人との出会いにも恵まれ、アムステルダムは私にチャンスをくれた人生のターニングポイントだったと言えると思います。
入試全般にかかわるアドミッションセンター長も兼務されています。
中本 現代は少子化であると同時に、部活をやっている子どもも減ってきており、体育大の志願者ってやはりとても減ってきているんですね。このまま減り続けると、この業界で育ったことを大事にする人たちが減っていくことになり、最終的に体育やスポーツ科学を学べる大学は社会から必要とされないものになってしまう可能性だってなくはない。そう考えると、アドミッションセンターの役割って、我々の仲間を増やす作業なんだろうなーと思いながらやっています。だから少しでも興味ある高校生にこの業界の面白さを伝えて、本学に入ってきて楽しんでほしいなって思うし、極端に言えば心理学に興味があってスポーツにちょっと興味がある、生理学や医学に強い興味がある、っていう生徒にも、こっちの世界でも案外面白いよってことを伝えて、仲間を増やしたいな~っていう、そういう思いでやっています。令和9年度からの新しい入試は、総合型選抜には実技を課さない予定ですので、スポーツをする・みる・ささえるの「みる・ささえる」、例えばスポーツ専門のライターをやりたい、でもスポーツは苦手、みたいな人にもうち大学に入ってきてもらって、スポーツを一緒に盛り上げていけたら、と思います。
学生に期待することは?
中本 とにかく楽しんでほしいなと思います。うちの学生って、壁を打ち破るためにドカドカと進んでいくんですよね。私が彼らと会うのは卒業論文が多いのですが、その一方で、できないことに対して割とネガティブに悩んだりしています。でも、彼らは失敗することの先に上達があることをとてもよく知っているんですね。スポーツで培った問題解決能力を応用すれば、社会に出てからたとえどんな困難にぶつかったとしても乗り越えていけると思うので、悩んでいることこそが次のチャンスにつながったりもするし、「人生スポーツ」ぐらいの感覚で、楽しく生きてほしいなって思っています。
好きな言葉や座右の銘にしている言葉はありますか?
中本 “頑張る”って言葉がすごい好きです。頑張るとはがむしゃらに何かをやることではなくて、かたくなだったり、頑固だったり、信念を貫く、張り通す、っていうのが頑張るだと思っているので。しんどいときやうまくいっていなくて苦しいときって、自分に信念がないときで、自分が何をしたくて生きているのかが見えてくると、モチベーション高く毎日を過ごせる気がします。たとえマイナーな研究でも、自分のお陰で1人を救えたとか、研究ってそういうことがモチベーションになって続けられるのだと思います。信念を曲げずにかつ自由に生きたい、っていうところは、高校生の頃からずっと変わっていないですね。
最後に、中本先生の今後の目標を教えてください。
中本 1つは今やっているVRの研究で、社会実装をしていきたい。研究の世界にだけとどまるのではなく、実際に社会の中に今自分が描いている研究の世界というものを埋めてみたいと思っています。筋トレって昔はなかったけれど、今はみんながやる時代になったのと同じように、知覚運動制御を専門にしているトレーナーが当たり前のように存在している時代をつくっていきたいです。もうひとつは、科学者として世界最高峰の著名雑誌に掲載されるような研究をしたい。この2つはここ数年思い続けていることですね。
※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。