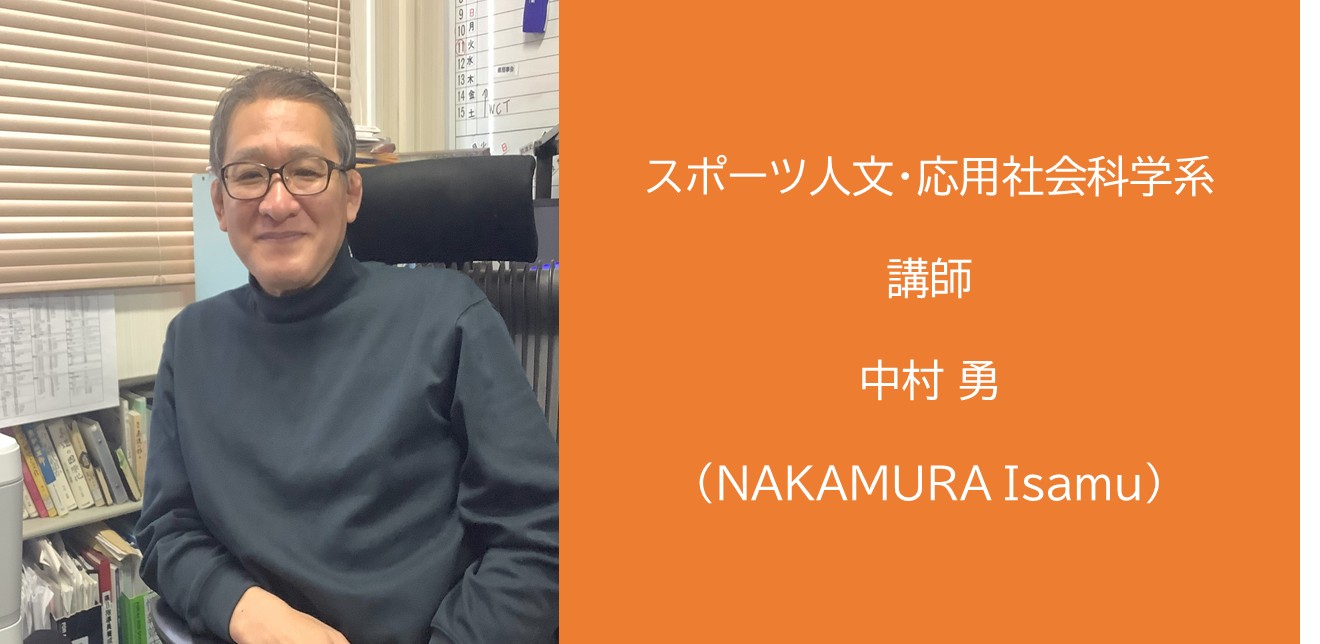
無口でおとなしく、表には出ない控えめな印象を受ける。実際その通りなのだが、数年前、「キャリアデザインⅠ」の授業で元阪神タイガースの故横田慎太郎さん講演会を行うことになり、打ち合わせを重ねる中で中村勇先生に対して抱いていたイメージが変わった。資料を手際よくささっとつくり、前向きにどんどん進めていく。不安材料を一つひとつスピーディーにクリアにしていき、最後まで協力的でそつがなかった。柔道部の監督も務める。高校生に人気の柔道界のYouTuberにも敏感で、時代についていくフレキシブルさを持ち合わせていることにも驚かされた。NCAA全米学生柔道選手権で、2年連続優勝の実績も。柔道の精神を大切にする、やさしさの中にも男気のある生粋の薩摩隼人である。
研究内容をひとことで教えてください。
中村 国際柔道の国際化に関する研究をしています。柔道は1882年、嘉納治五郎氏によって創始されました。柔道の国際史を紐解くと、最初は伝統的な日本古来の武術というよりはスポーツとして1964年の東京オリンピックで火が付き、オリンピック種目競技として広がっていったことがわかります。最初の頃、海外の柔道は日本とレベルが段違いで、日本から指導者を送り込んでいました。そうしてだんだん強くなってくると、70年代以降今度は日本がライバルになってきて、何とか日本に勝とうという動きが出てきました。日本の柔道は正しく組んでしっかりと技をかけていくスタイルなので、まともにやっていては勝てない。そこで正しく組ませない、一本取られない、足元を狙って倒してあとはひたすら守り切る、といった“ネガティブ柔道”が流行りだすんです。紆余曲折を経て、2000年頃から日本がまた強くなるのですが、世界的な人気スポーツになった柔道が、日本から世界へどんな感じで広がっていったのか、というのが現在の研究内容になります。
中村先生が以前取り組んでおられた「青色柔道衣採用に関する研究」に興味を持ちました。
中村 柔道発祥の地日本において清い心の象徴として柔道衣は白、またはオフホワイトが当たり前でした。ところがルール改正を求める動きが出てきて。その頃私はちょうどアメリカから帰国して筑波大学の大学院に在学中でしたので、1995~1997年の2年間、全日本柔道連盟でカラー柔道衣対策チームとして仕事をしました。日本はカラー導入に猛反対でしたが、当時は国際柔道連盟の組織の中でもヨーロッパが主体でしたから、青こそ国際化の象徴だ、みたいな感じで、結局1997年に国際柔道連盟の総会でカラー柔道衣の導入が決定されてしまったのです。しかし、当初伝統を打ち破った青い柔道こそが現代柔道の象徴みたいな位置づけだったのが、現在は表彰式など公式の場では白着用が義務付けられるようになっています。日本が何か言ったわけではなく、国際柔道連盟が伝統重視の方向にルールを変えたのです。嘉納氏が興した柔道の総本山・講道館では今でも国際柔道連盟の講習会などが開催され、その教えは今日に引き継がれています。今また柔道は原点回帰されてきていると感じます。
中村先生は講道館柔道6段です。柔道を始めたのはいつですか。
中村 中学生になってから未経験の初心者で柔道部に入りました。両親には「人が良すぎてやさしすぎる性格」と思われていたようで、人と競い合うのが苦手なタイプを心配した親に勧められました。専門の指導者はいなかったし、先輩たちも強くなかったので、最初の頃は全然楽しくなくてやる気もなかったですね。中2のときに外部から指導者の先生が来てくださり、初めてきちんと教えてもらったのですが、気が付いたら試合で勝つようになっていました。
それで鹿児島県立鶴丸高校に進学しても柔道部に?
中村 鶴丸の柔道部は弱いだろうと思って期待していなかったのですが、中学時代に強かった顔見知りの選手が複数来ていてびっくりしました。指導者の西川達也先生が鹿児島県柔道会の役員をされていたので、県の強化練習会に参加させてもらって、それで強くなりました。県で優勝するような選手に負けなくなってきて「あれ、もしかして俺、強いんじゃない?」と(笑)。ただ、筑波大学の柔道部は入ったことを後悔するぐらい、強い人ばかりでした。
中村先生が考える、鹿屋体育大学の魅力は?
中村 学生が純粋ですよね。トレーニングする場所はたくさんあるし、施設は広くて充実しているし、競技に打ち込める環境はものすごく整っていると思います。大会に出場するときに遠征地までの距離が遠いという不便さはありますが、食事は安くて美味しいし、温泉はあるし、生活費も都会に比べてかからないのでとても恵まれていると思います。
2020年3月に卒業した福田大悟さんが、2024年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会の60㎏級で優勝しました。卒業生の活躍にも目が離せません。
中村 福田選手の優勝は近年では2015年の講道館杯で優勝した竪山将選手に続く2人目で、国際大会である柔道グランドスラム東京にも出場しました。最近では警察官や刑務官になって柔道を続けている卒業生が教官や指導者になったり、全日本選手権の決勝戦で審判を務めるなど、重要なポジションに就いている卒業生も増えてきました。柔道の名門大学と比較しても遜色ないぐらい、男女共に各地で卒業生が活躍しています。
全日本柔道連盟やJOC強化スタッフ柔道戦略・技術担当など、さまざまな委員活動もされています。具体的にはどんなことをしてこられたのでしょう。
中村 北京オリンピックの頃に柔道の試合でレスリングのようなタックルが増えてきて、明らかに柔道の技ではないよね、というような試合が増えてきたんです。「こういう試合を見て、子どもたちが柔道をやりたくなると思う?」と、タックルを禁止させるためのプレゼン資料をつくり、それが国際柔道連盟のルール改定につながったことは大きかったですね。全日本柔道連盟が設置した、「公認柔道指導者資格制度」にもゼロからかかわらせていただきました。
柔道部の監督として、今後の目標は?
中村 コロナが明けて再び国際交流が動き出しているので、国際的なレベルを意識した強化ができてくればと考えています。関東・関西の大学のトップチームは常に国際大会を意識しているので、うちの学生にもそうなってほしいと思っています。個人戦全国優勝、団体戦ベスト8の目標を達成したいです。
最後に、中村先生の今後の目標を教えてください。
中村 勝ち負けではなく広い視野を持って、柔道の経験を通して社会に貢献できるような人材を育てていきたいです。もちろん柔道をしている、していないにかかわらず、鹿屋体育大学で学んだことを生かしてほしい。「日本の常識は世界の非常識」という言葉がありますが、狭い視野で自分勝手にならないよう、柔道の常識は世界の非常識といった意識は常に持っていたいと思います。
※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。