青山学院大学 教育人間科学研究科心理学専攻 特任准教授 畠中 智惠さん
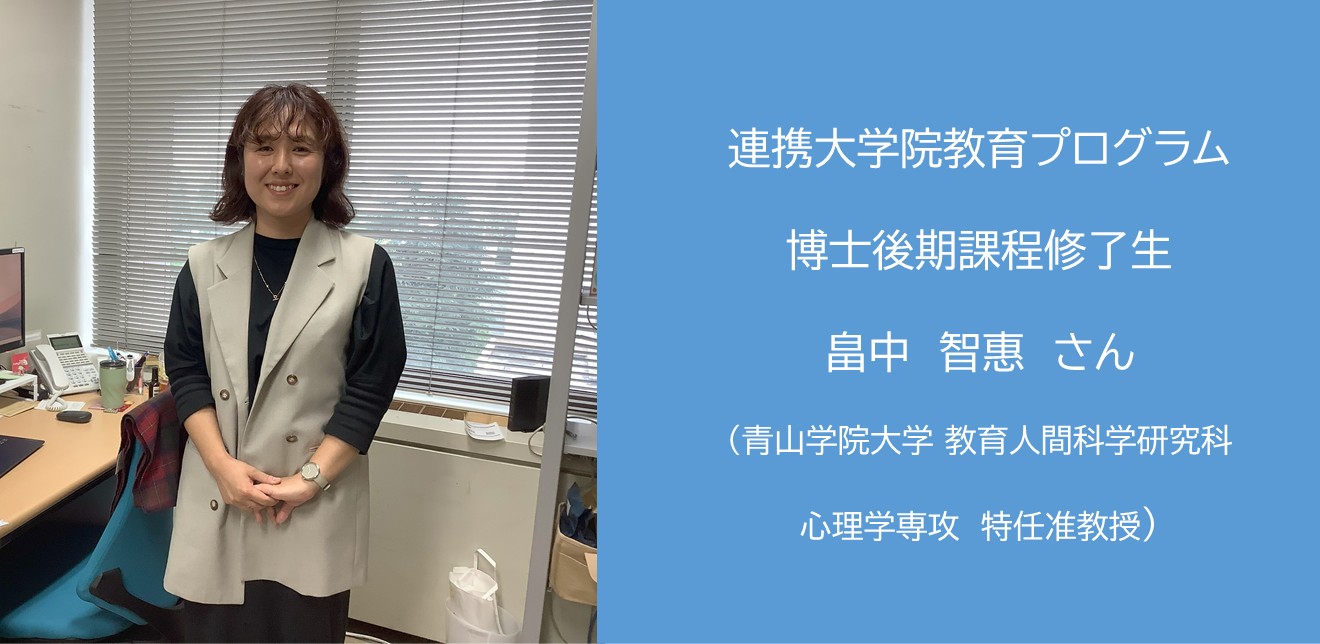
東京・渋谷の青山学院大学で特任准教授を務める、畠中智惠さん。鹿屋体育大学大学院で体育学博士を取得した後、大学教員の道へ進んだ連携大学院受講生だ。笑顔が素敵でやさしい雰囲気だが、高校時代は女子バスケットボール部のキャプテンも務めたというだけあって一度決めたら最後までやり通す芯の強さものぞく。志を高く持ち、常に前を向いてステップアップしてきたのだと思う。表参道駅から徒歩5分、おしゃれな大学として人気の青山キャンパスの研究室で話を聞いた。
心理学を学ぼうと思ったのは?
畠中 実家が鹿児島県の肝付町でお寺と「高山こども園」を経営しており、小さい頃から両親の話を聞いている中で、子どもが大人になっていく成長の過程で親子の関係、大人と子どもの関係はとても大事なことなのだと子ども心に感じていました。さらに父が保護司もしていたので、非行少年の支援にかかわる父の姿を見て、なぜ非行に走ってしまうのだろうと考え、心理学に興味を持っていろいろ調べていくうちに臨床心理士という資格があることを知り、高校卒業後は心理学科のある大学に進学しました。
鹿屋体育大学の連携大学院に行こうと思ったきっかけは?
畠中 森司朗先生(スポーツ人文・応用社会科学系教授)の研究フィールドのひとつが、実家の保育園だったんです。父から、子どもの遊びから子どもの発達や人間関係の構築などを研究している先生がいると聞いて、森先生の研究内容に興味を持ちました。大学院の修士課程で研究がとても面白かったので、再び研究をやりたいと思っていたこともあります。連携大学院について森先生と中本浩揮先生(同系教授)のお二人から話を伺ったところ、とても楽しそうでワクワクして、単純なんですが「博士に行こう!」と決めました。
実際に行ってみてどうでしたか。
畠中 それまでは心理学の中でも臨床心理学や社会心理学の視点でしか勉強してきていなかったのですが、連携大学院では脳神経の話や比較心理学、人体とは、といったような多面的に人を捉える“知見”といったことを享受してもらえました。素晴らしい先生方と出会えたのも、鹿屋体育大学連携大学院の魅力だと思います。先生だけでなく、同期のメンバーにも恵まれて雰囲気もすごくよかったです。研究するにはたくさんのデータを取らないといけないのですが、その辺りもものすごくスムーズにいって、環境的にも恵まれていたので、体育大に行ってよかったと思っています。
苦労したことは?
畠中 いわゆる一般の心理学しか学んでいなかったので、体育大は系統が異なっていて、体育大ならではの専門用語の意味が最初はまったく分からなかったことです。連携大学院の先生方にとってはスタンダードな知識に追いついていくのが大変でしたが、紹介していただいた本を読んだりしていくうちに少しずつ理解できるようになりました。ゼミもきつかったし、発表することも本来苦手なので大変でしたが、面白さの方が勝っていたのでついていけたのだと思います。公認心理師の受験勉強も並行してやっていたので、いま振り返っても大変だったと思いますが、子どもに関する研究を続けたいという想いと、自分の中に知識を溜めていくのが楽しかったんだと思います。苦しかったけれど自分で決めたことなので、まだまだ突き詰めていきたいと思えました。
なぜ大学の先生に?
畠中 卒論も修士論文も大学生を対象にしたコミュニケーションの課題をテーマにしたのですが、研究をしていくうちに青年期よりも幼児期の経験がとても大事だということに行き着きました。連携大学院在籍中に、教員募集をしている大学があることを知ったのが大学教員としてのスタートのきっかけです。最初の大学は保育士や幼稚園教諭になりたい学生が入学してくる学科でしたので、子どもってこういうふうに捉えるべきだよねっていうところをきちんと培った卒業生を現場に送り込みたいと思っていましたし、そのことに自分が少しでも貢献できるならうれしいという思いもありました。
これから連携大学院に行きたいと思っている人にアドバイスがあれば。
畠中 知識って能動的に行動を起こさなければ得られなかったりするんですけど、連携大学院ではいろんな先生が授業をしてくださるし、中間発表のような形の論文指導研究会では、そんな視点考えもしなかった、といったようなその先生ならではの観点からフィードバックがくるので、私自身思考の幅がかなり広がりました。知識が自然に入ってくるので、研究を続けていく上でとてもいい刺激になると思います。ただ、視点が広がるので混乱したり、収拾がつかなくなったりすることもあります。そこで、収束する力が必要になってきます。情報の取捨選択をうまくやっていかないと、前には進まないということを強く感じました。
最後に今後の夢を教えてください。
畠中 子どもの遊びを研究テーマにしているのですが、遊ぶことってとても大事で、運動能力や身体的な発達はもちろん、パーソナリティーの発達や社会性の発達にとっても重要な部分になってくるんです。でも、子どもの遊びの本質を考えて遊びの時間を重視する保育園って意外とないんですよ。勉強やプログラム、カリキュラムがあって、遊び以外のことをいっぱいする保育園が多いんです。うちの実家の保育園は遊びをメインでやっていて、私が言うのも変なんですけどものすごくいい保育園なんです。こんな保育園が増えてほしいなっていう思いはずっとあります。今後研究を続けていくことで「遊ぶ」ってすごい大事なんだよ、っていうところをもうちょっと広めていくことに少しでも貢献できれば、それが実家への恩返しにもなるのかなと思っています。あとは研究者としての実績をつくって、次のステップに繋げられたらと思います。


【プロフィール】
はたなか・ともえ。1989(平成元)年8月5日、鹿児島県肝付町生まれ。鹿児島県立鹿屋高等学校、東京女子大学文理学部心理学科卒業。2014年3月、青山学院大学大学院教育人間科学研究科心理学専攻臨床心理学コース修了。2020年9月、鹿屋体育大学大学院体育学研究科体育学専攻博士後期課程(体育学・スポーツ科学連携大学院教育プログラム)修了。学校法人純真学園純真短期大学こども学科助教等を経て、現在青山学院大学教育人間科学研究所心理学専攻特任准教授。
(取材・文/西 みやび)
※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。