九州中央リハビリテーション学院 理学療法学科 副学科長 中山 貴文さん
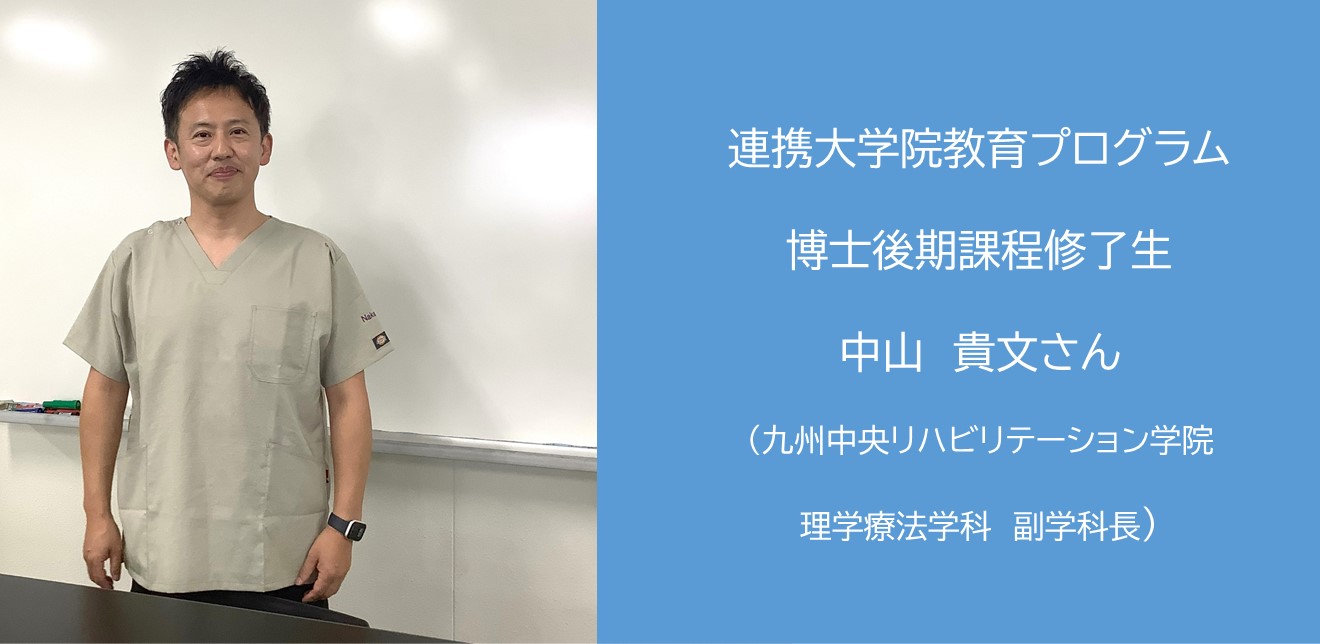
熊本にある九州中央リハビリテーション学院で、理学療法学科の副学科長を務める中山貴文さん。鹿屋体育大学の大学院に在籍しながら、連携校の熊本大学を研究活動の基盤に置き、博士後期課程を単位修得満期退学して体育学の博士の学位を取得した連携大学院受講生だ。昨年は熊本大学大学院教育学研究科の井福裕俊教授、坂本将基准教授との研究グループの筆頭著者として「第36回日本体力医学会学会賞(体力科学)」を受賞、「どうせやるならとことんやる性格」の自己分析通り、研究への探求心も強く、多方面で活躍している。「私でお役に立てるのなら」と、取材にも快く応じてもらった。受講生としての生の声を聞いた。
中山先生のこれまでの経歴を教えてください。
中山 熊本大学を卒業後、手に職をつけたいと思い、アルバイトをしながら理学療法の専門学校の夜間部に通って理学療法士の資格を取得しました。そのときのご縁で、千葉県にある船橋整形外科病院に就職したのですが、日本全国の中でもスポーツ医学の最先端をいく施設で、院長先生が臨床と研究は両輪で両方しっかりやらないといけないという考えの方でしたので、理学療法士として働きながら研究活動も並行して行っていました。周りは優秀な先生ばかりで、私の基盤をつくってもらったと言っても過言ではないほど、ものすごい刺激を受ける日々でした。ただ、私自身は当時は大学院を出ていませんでしたので、大学院に行って研究とはどういうものなのかを一度きちんと学びたいと思っていました。6年間勤務した後、熊本にUターンして九州中央リハビリテーション学院の教員になり、2015年、38歳の時に働きながら母校でもある熊本大学の大学院修士課程に進学しました。
連携大学院のことを知ったのは?
中山 これもご縁だと思うのですが、熊本大学大学院教育学研究科の井福裕俊教授は学部時代の恩師、坂本将基准教授とは大学の同期で井福ゼミの同じ1期生でした。熊大の教育学部には修士課程までしかなく、井福教授が連携大学院のご担当をされていましたので、最初から修士課程修了後は連携大学院で博士号取得を目指して頑張ろうと思っていました。
連携大学院の良さは?
中山 基本はオンラインでOKなので、地元にいながら今やっていること、たとえば仕事などを継続しつつ、修士や博士を取得できることだと思います。私自身は鹿屋体育大学の先生に、せっかくなので対面でやりましょうと声をかけていただいたこともあり、鹿屋にも何度か足を運びました。連携大学院説明会の時にいただいたパンフレットに、対象者として大学教員、研究職、理学療法士、栄養士、作業療法士、学校教員、地域社会の健康スポーツ指導者、トレーニング指導者など、さまざまな分野の方が挙げられており、船橋の病院では学者だけでなく、いろんな分野のプロフェッショナルがリードして、さらに自分の分野を深く掘り下げていくような働き方で成り立っている環境で仕事をしておりましたので、いくつもの研究分野が隣接しているような連携大学院の理念に「あー、これだ!」と、強い魅力を感じました。都会ではスペシャリストが求められますが、地方ではどちらかといえば幅広い知識や経験を持ちオールマイティーに活躍できるジェネラリストの方が必要とされていると思います。問題解決のためには、理学療法の考え方以外にも幅広いさまざまな視点が必要だと思いますので、連携大学院でいろんな先生方から学べたことは、とてもプラスになりました。鹿屋体育大学の連携大学院がなければ博士の学位は取れていませんので、存在はとても大きかったですね。
在籍中で印象に残っていることは?
中山 毎年11月に中間発表みたいな形で論文指導研究会があり、学位を取られた先輩の講演やディスカッション、論文指導やアドバイスもいただけて、年1回の交流を私自身はとても楽しみにしていました。そこでご指摘いただくご意見というのは、国立の体育学・スポーツ科学連携大学院ならではのレベルの高さで、私には理学療法の業界にいる後輩たちにもぜひ見てほしい世界だという気持ちがものすごく強いです。たとえば病院に来られる方は、ある程度病気が進んでいるわけですから、我々理学療法士の分野ではなかなか予防はできないのが現状です。しかし、連携大学院でさまざまな分野の方々と連携することで新たな可能性が広がっていくことを体感することができ、私の中ではああまさにコレだなっていう実感がすごくありました。“体育学・スポーツ科学”の連携大学院で学んだことで、井の中の蛙にならず、物事を科学的に考えられるようになったのも大きかったですね。
最後にこれから連携大学院で学ぶことを考えている方へ、アドバイスをお願いします。
中山 実際に鹿屋に通わなくても、連携校で同じレベルの研究に携わることができるのが連携大学院の魅力だと思います。連携大学院の先生方は素晴らしい先生が多いので、実際に入学して学びを深めたことは、今後に必ずつながってくると思います。チャンスがあるのであれば、ぜひ受講をおススメします。
-1386x924.jpg)

【プロフィール】
なかやま・たかふみ。1977(昭和52)年4月19日、熊本県生まれ。熊本大学教育学部生涯スポーツ福祉課程卒業。西日本リハビリテーション学院理学療法学科卒業。船橋整形外科病院スポーツ医学センター理学診療部に6年間勤務後、熊本へUターン。九州中央リハビリテーション学院に教員として勤務。熊本大学大学院教育学研究科修士課程修了。2019年3月、鹿屋体育大学大学院体育学研究科体育学専攻博士後期課程(体育学・スポーツ科学連携大学院教育プログラム)単位修得満期退学。2023年3月、体育学の学位取得(論文博士)。現在、九州中央リハビリテーション学院理学療法学科副学科長。
(取材・文/西 みやび)
※所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。